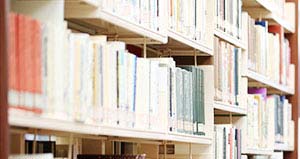福祉2025.9.18
「ソーシャルワーク」という支援とは
#ソーシャルワーク #環境 #ストレス
その人らしさを支えるソーシャルワーク~人と環境に働きかける~
人は困難に直面しても自分の力で乗り越える力を持っていますが、人間関係や仕事の悩みなど環境の影響によって力を発揮できないことがあります。ソーシャルワーカーは、困っている人の話を聴き(面接)、家族や職場の人と協力したり(環境の調整)、制度やサービスを活用しながら、その人が本来の力を発揮できるように支援していきます。
例えば、会社をリストラされて不安で眠れない人に、精神科医は睡眠薬を処方し、公認心理師はカウンセリングをするかもしれません。精神保健福祉士(ソーシャルワーカー)は話を聴き、「どのような仕事や生活を望んでいるか」を一緒に考えながら仕事探しを一緒に行います。仕事が見つかって安心できると、不安や不眠が自然と良くなることがあります。
ソーシャルワーカーは、その人が望む生活を実現できるように、一緒に考えて、かかわりながら行動する"伴走者"です。
人間関係のストレスが軽減する!?
ソーシャルワークを学んでからは、人間関係で上手くいかないときに、相手の置かれている環境を見て、こういう事情があったのかもしれないと、考えるようになりました。
以前、私は他職種の上司に理不尽な叱責を受けたことがありました。その人は、人手不足で多忙など環境の大変さがいくつもあり、つい感情的になってしまったのかもしれません。そう考えると、自分のミスは反省しつつも、「必要以上に自分を責めなくていいんだ」と思えるようになりました。人との関係を目の前の言動だけではなく、その人の背景や環境も含めて広い視点で見られるようになったと感じます。そのおかげで、人間関係でのストレスが軽減されたように思います。
ソーシャルワークは、どのような背景や気持ちを持っているのかを、その人と一緒に考えながら理解していきます。人間福祉学科で学ぶと、人や社会をいろいろな見方で考えられるようになります。あなたも新しい視点を持ってみませんか?
鹿内 佐和子
准教授
人間学部 人間福祉学科
大学病院の総合相談室や精神科デイケア、精神疾患の方の相談支援施設でソーシャルワーカーとして20年以上仕事をしていました。精神疾患の方が病気を抱えながらも自分らしく回復していくプロセスのことをリカバリープロセスと言いますが、どのような経験やサポートがリカバリーを後押しするのか、どのような環境が必要とされるのかを、当事者の方や支援者の方にインタビュー調査をして分析しているところです。