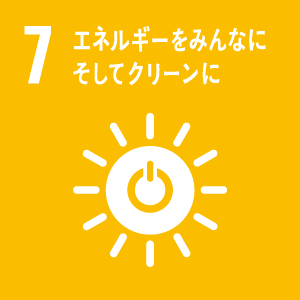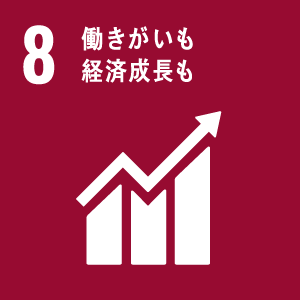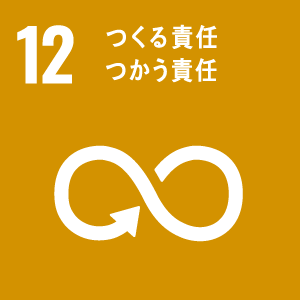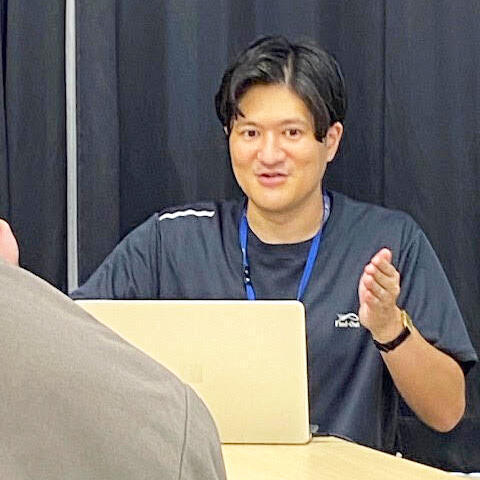-

丸井氏との意見交換 -
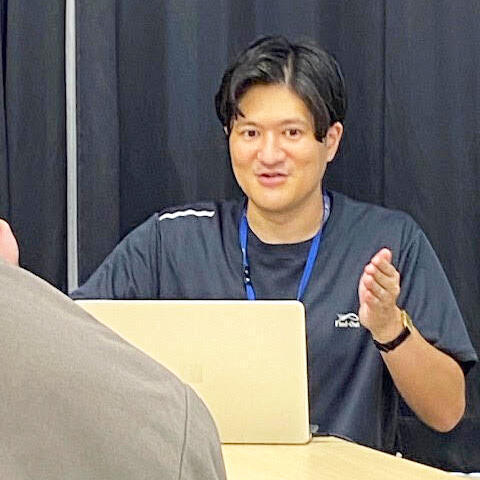
レクチャーする丸井氏
社会学部地域社会学科<地域・ひとづくりコース>の飛田満教授が担当する「地域社会学応用演習」では、SDGsをテーマとして取り上げ、持続可能な社会の実現に向けて、私たちの身近な日常生活をSDGsの視点から捉え直す、ゼミ形式の授業を行っています。
7月22日(火)の授業では、株式会社丸幸の丸井剛氏をゲストスピーカーにお招きし、「私たちの廃棄物の未来を探究」というテーマでご講義いただき、質疑応答・意見交換を行いました。
株式会社丸幸は千葉県を中心に関東一帯に展開する産業廃棄物と一般廃棄物の総合リサイクル企業で、丸井氏は同社にあって新規事業開発や廃棄物関連の環境教育(小学校から大学まで)に取り組んでいます。
講義セクションでは、家庭ごみと事業ごみの違い、事業系一般廃棄物と産業廃棄物に関する基礎知識からはじまって、中間処理施設のリアルと作業内容、化石燃料に代わる固形燃料RPFについて、とても分かりやすく画像や映像を使ってご説明いただきました。
質疑応答・意見交換では、ごみの分別方法や処理方法に関するさまざまな問題が議論される中で、自治体ごとにごみの回収方法が異なること、中間処理施設には厄介な混合廃棄物がたくさん運び込まれること、リチウムイオン電池の混じったごみの火災事故が絶えないこと、プラスチックごみが効果的な固形燃料になることなど、リアルなお話に考えさせられました。
そして大きな収穫として、廃棄物・リサイクル業界における現場での驚きの事実とともに、サステナブルな社会の実現や社会課題の解決に向けたビジネスとしての魅力と可能性について知ることができました。