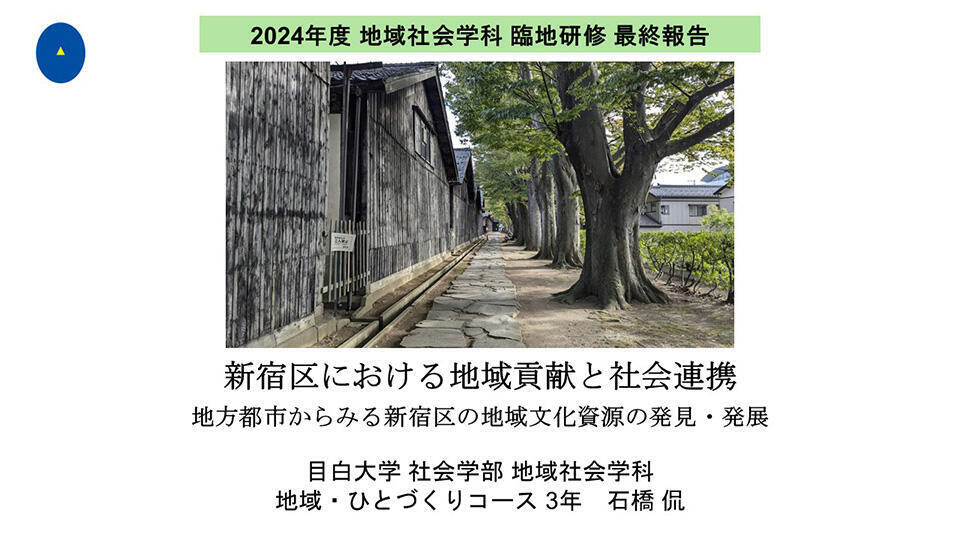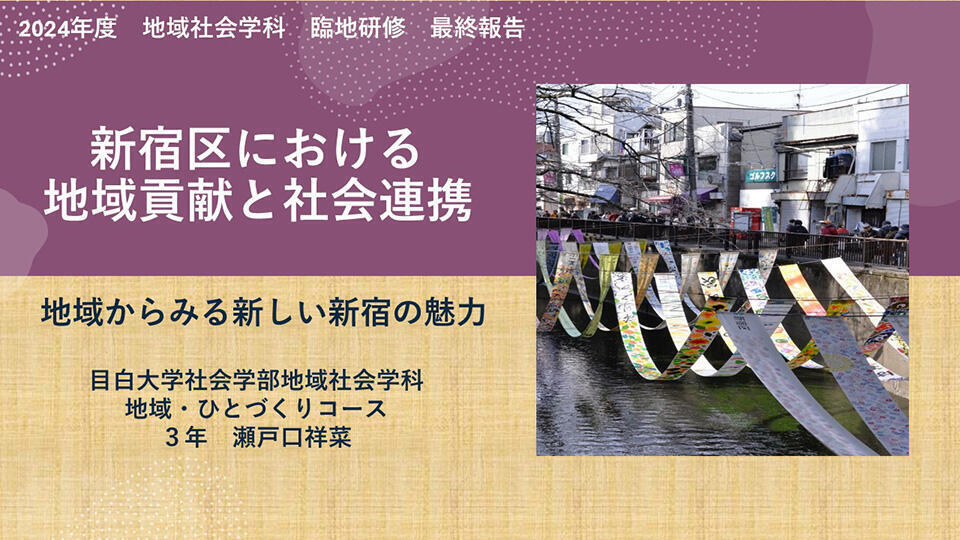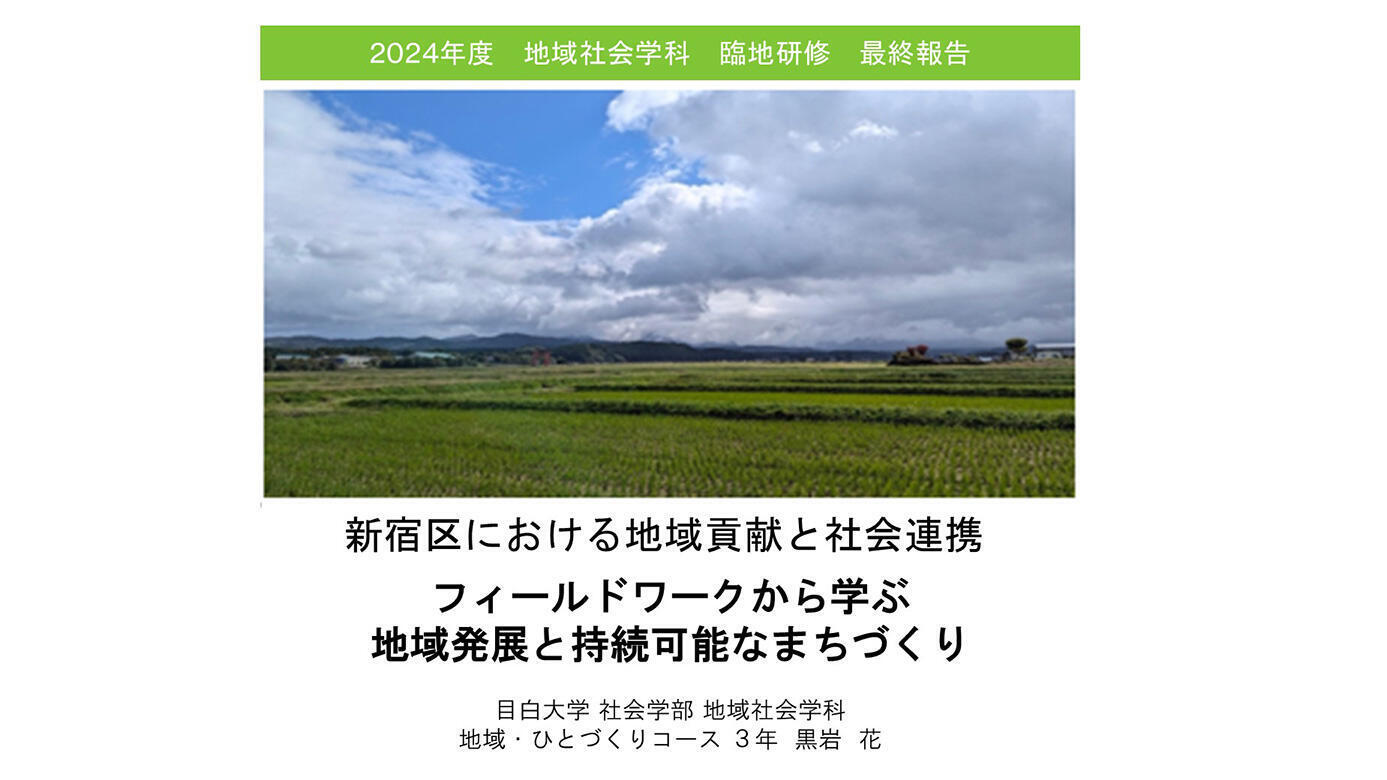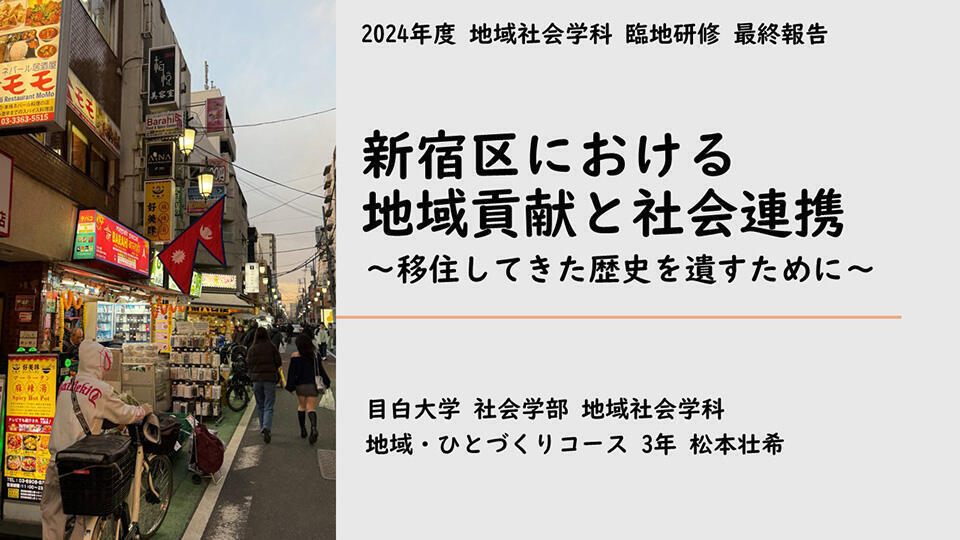-

発表の様子 -

動画の視聴
4月29日(火)、社会学部地域社会学科<地域・ひとづくりコース>で、2024年度「臨地研修」報告会を開催しました。
「臨地研修」とは、学生自らがフィールド調査を行ったり、ボランティア体験をしたり、地域貢献活動に参加したりなどして、合計60時間以上の学外研修を積み、最終報告書を提出することで単位が認定されるという科目で、この「現場での学び」を<地域・ひとづくりコース>の教員はスクラムを組んで後押ししています。
特に本コースの臨地研修は、目白大学が新宿区と包括連携協定を結んでいることから「新宿区における地域貢献と社会連携」という大きな共通テーマを掲げ、そのテーマの下で、新宿区と直接関わるプログラム(コアプログラム)と新宿区との比較対象として他地域を扱うプログラム(サブプログラム)、さらに自主企画プログラムも含めて、20以上の多種多彩なプログラムが提案され、実施されました。
昨年5月の報告会・説明会から年度末まで長期にわたって、多くの学生がいくつものプログラムに参加して研修を行ってきましたが、その中で最終報告書を提出した4名の学生に成果報告をしてもらいました。このうち2名は同じ時間に他の授業を履修しているため、事前に収録された動画による報告となりました。
2024年度「臨地研修」成果報告会:発表内容
石橋 侃さん
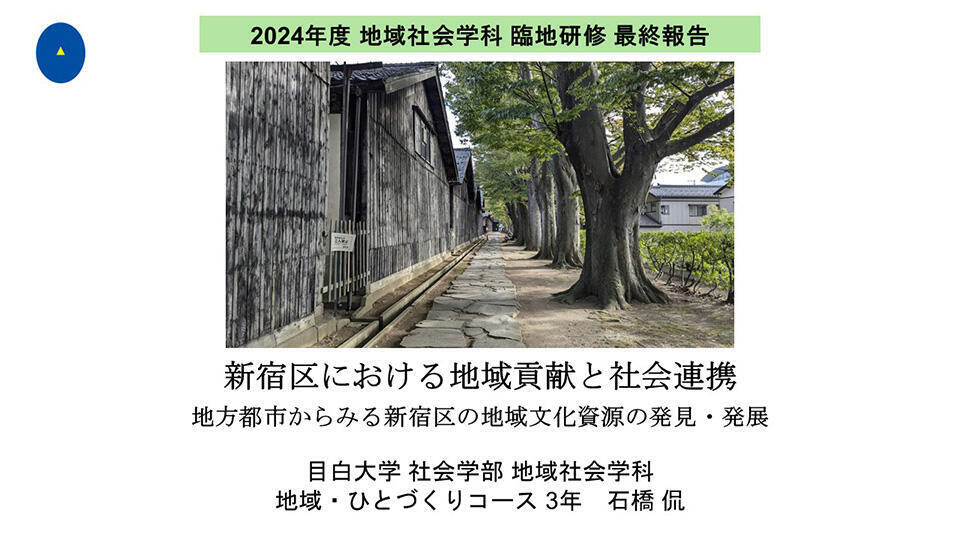
「新宿区における地域貢献と社会連携~地方都市からみる新宿区の地域文化資源の発見・発展~」
- 第1章:スポーツチームと地域の繋がり
~新宿区が抱える地域課題とは~ - 第2章:"遊び"とは何か、遊びの場から街の構造を考えてみる
- 第3章:この地域の地域文化資源は何か
~新宿区との相違点・類似点は何か~
- 第1章:スポーツチームと地域の繋がり
-
瀬戸口 祥菜さん
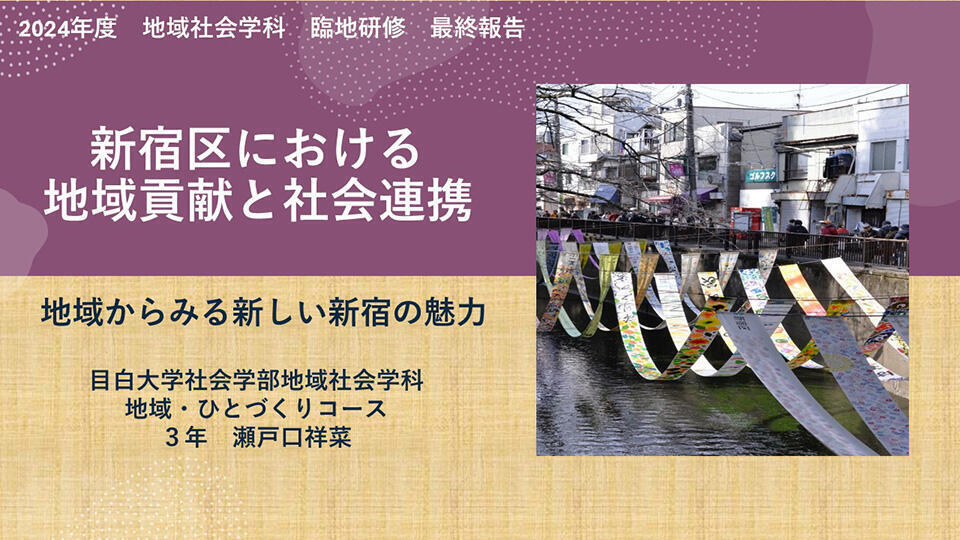
「新宿区における地域貢献と社会連携~地域からみる新しい新宿の魅力~」
- 第1章:新宿区の環境問題の現状とその対策
- 第2章:ボッチャからみるスポーツを通じたつながり
- 第3章:地域住民により受け継がれる染色文化
-
黒岩 花さん
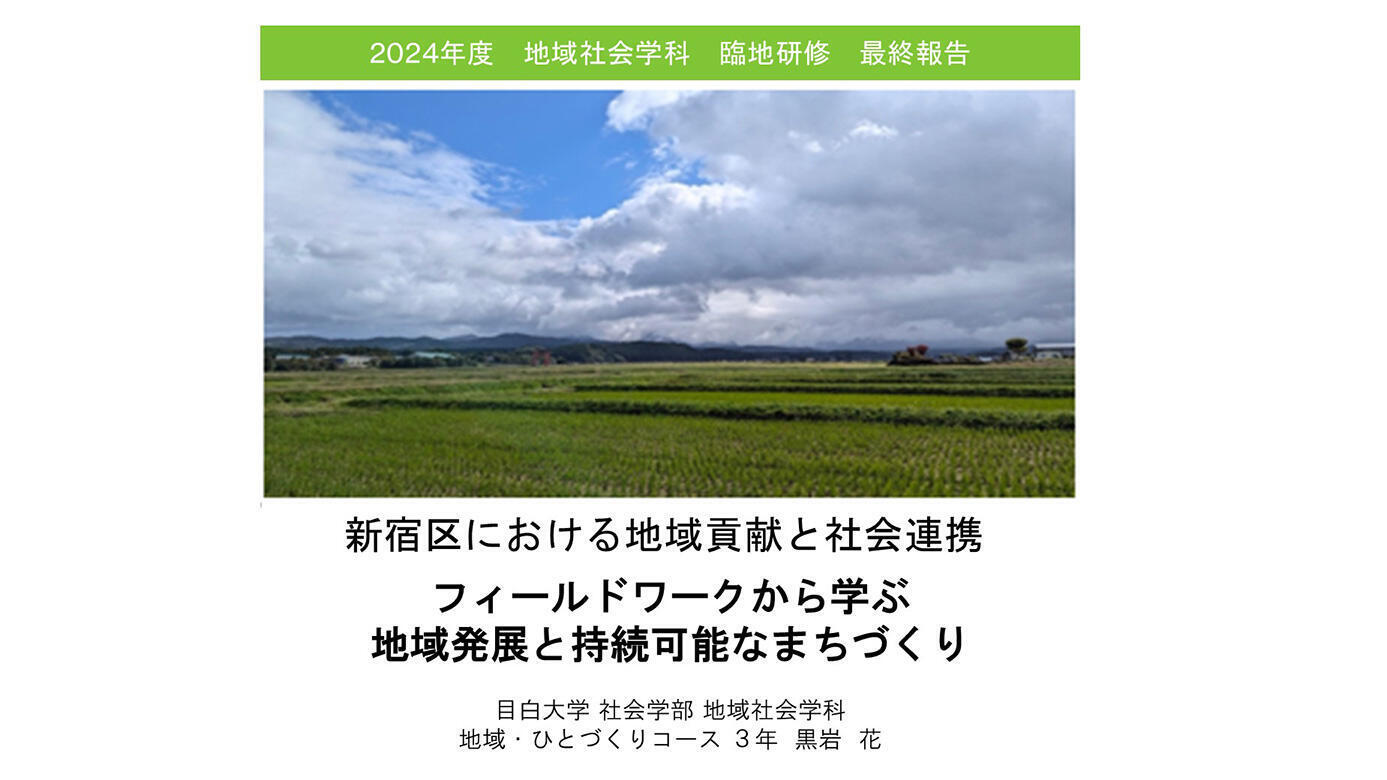
「新宿区における地域貢献と社会連携~フィールドワークから学ぶ地域発展と持続可能なまちづくり~」
- 第1章:「染の小道」に長期インターンとして参加する
- 第2章:山形県酒田市と鶴岡市からみる歴史
- 第3章:NPO法人新宿環境活動ネットのボランティア活動に参加する
-
松本 壮希さん
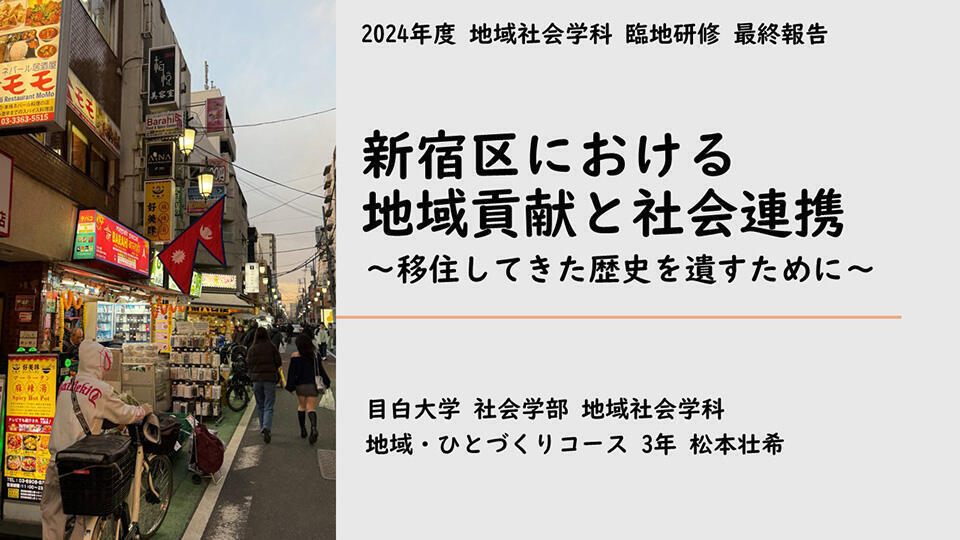
「新宿区における地域貢献と社会連携~移住してきた歴史を遺すために~」
- 第1章:地域社会における文化の保護と継承
- 第2章:移住した人の歴史とその遺し方
- 第3章:移住してきた人の歴史とその遺し方
- 第4章:地球が抱える問題と在留外国人
本報告会は2年生の「臨地研修」履修準備のため、必修科目「専門とキャリアA」の時間を使って行われました。2年生は先輩の成果報告を聞く貴重な機会となるとともに、実際多くの刺激とヒントを得たようで、4人の報告に対して以下のような感想も聞かれました。
学生の感想
・石橋さんの報告では3つの活動内容が挙げられたが、KPMGでの活動ではスポーツと地域の関わりという点から主体的に解決策を考えられており、新宿区の遊びの場では新宿についての理解を深められており、地方都市の地域文化資源では学生が地域文化資源にどう関わるかを考えられていた。これらの活動はとても有意義に見え、興味があるため参加してみたいと思った。
・新宿区の"遊び場"の現地調査における考察で、子どもは遊具等を用いて自らでルールを決めて遊ぶといった創造的な遊戯を行うのに対し、大人は場所毎におけるコンテンツとしての消費しか出来ない=自由の喪失といった観点が批判的?な視点も含めつつ、とても痛快で現代社会のコンテンツ化されてしまった構造を的確に捉えたからこそ出来る考察だと思った。
・瀬戸口さんの報告で、学生は今までの学びを実践的に活かせる、社会人はアイデアを学生から得る事ができ新しい事業に取り組む事ができる、というところが印象的だった。学生と社会人が共同で地域のイベントを行うとうまくいかないことも多々あるが、プラスとなるものが多く地域にも貢献することもできる。発表のまとめにもあった、隠れている魅力もまだ多くあるため、地域単位という言葉を大切に考えていきながら取り組んでいきたい。
・黒岩さんの報告は、染の小道の実行側としての視点からの良かった点と改善点を俯瞰的な視点から捉えており、今後の活動にも生かせるような、次につながるような反省点を具体的に挙げていたのでとても分かりやすい発表だった。地域住民のみでなく、同じく実行側での新たな交流を深めることもしていたので、多角的な視点からもコミュニケーションを広げていく姿勢にも素晴らしいと感じた。また、新宿の活動において臨地研修が終わった後でも、そこでのご縁を大切にし、そこで今後も働いているということにも驚いた。
・松本さんの報告から、「遺す」というのは共同性の高いことで成り立ち、お互いの文化を認め合うことで、異文化を受け入れた地域おこしをすることができ、経済面やその土地の文化でもお互いにプラスになっていると分かった。理想は上野や福生のような姿であるが、現状は新宿区大久保地区のように観光公害のような課題を抱える街も、観光面に特化し文化を築き、それぞれの街に良い部分もあるのではないかと考えた。しかし、地域住民の多様性を受け入れ、お互いに合わせた街に変わることにより、新しい文化に塗り替えられるのみでなく、従来の文化を遺すことができると考えた。