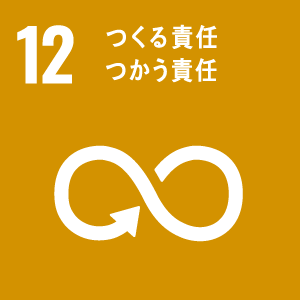-

キラキラ星とゴミ星人の登場
10月27日(日)、児童教育学科新聞委員会が「SDGsアクション」の企画で「人形げきで地球のゴミ問題を知ろう!!」を実施しました。
本企画は目白大学人間学部児童教育学科新聞委員会に所属している学生が、SDGs(持続可能な開発目標)の達成のために普段の生活の中で私たちができることを小学生に知ってもらいたいという思いから、生まれました。今回は、ゴミ問題に着目し人形劇やレクリエーションを通して地球のゴミ問題の現状や解決策を地域の小学生と共に考えました。
人形劇では、廃棄されるペットボトルや紙などを使用して人形を作りました。
人形劇のあらすじ
とてもきれいなキラキラ星がありました。ある日、ゴミゴミ星人がキラキラ星を攻撃したため、きれいだったキラキラ星はゴミだらけになってしまいました。しかし、キラキラ星の住民が、ゴミの分別に挑戦したことで、再び、きれいなキラキラ星を取り戻すことができました。
レクリエーションでは、新宿区の分別方法に沿って、可燃ゴミ・不燃ゴミ・ペットボトルの3種類のゴミの分別体験を行いました。ゴミのイラストを、種類ごとに分けて壁に貼り、困ったときに壁を見ると、ヒントになっているという工夫をしました。
ワークショップでは、ペットボトルのキャップを使ったストラップ作りを行いました。ペットボトルのキャップは、校内の方にも協力を呼びかけ、集めました。キャップを細かく刻み、それを自分の好きなように並べ、アイロンを使って熱し、完成させました。
新聞委員会では、毎年、SDGsアクションに挑戦しています。SDGsアクションを通し、地域の子どもたちと交流することで、小学校現場とは違った、また別の視点で物事を考えられるようになりました。今回の活動を通して学んだことは、教師になったときにも生かしていきたいです。
<学生の感想>
・子どもたちと一緒に、ゴミ問題について考える良い機会になりました。人形劇は少し緊張しましたが、夏休みから準備してきたものを披露することができて良かったです。ペットボトルのキャップからストラップを作るワークショップでは、大人も子どももみんなで楽しく活動することができ、普段できない貴重な体験ができました。
・SDGsアクションをやってみて、小学生を対象とした企画には、さまざまな配慮が必要だと感じました。劇のように物語として説明することで、小学生にも伝わりやすいことを実感しました。また小さいことの積み重ねをすることで、SDGsの問題が良い方向に行くということがわかりました。
・今回の活動を通して、たくさんのことを得ることができました。私は人形劇担当でしたが、人形劇はしたことがなく、本番どうなるのか不安でした。でもたくさんの人たちの協力もあり、最終的には素晴らしい人形劇に仕上がって本当に良かったです。多くのみなさんの前で人形を使ってセリフを話せたことは、これからの自分の自信にもつながりました。こんな最高な新聞委員の仲間と出会えて本当に良かったと思っています。
※この記事は新聞委員会の学生が担当しました。
-

ゴミの分別考え中 -

ストラップ作成中 -

かわいい作品ができました